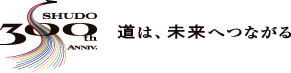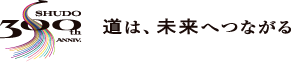MESSAGES
修道中学校 藏下一成教頭(中央)、株式会社NTTファシリティーズ中国支店 中村達哉氏(左)、株式会社フジタ広島支店 明賀朋昭氏(右)
VOL.3
〈座談会〉 修道300年の新たな「器」―
新校舎が導く“修道進化論”
─後編─
修道中学校・修道高等学校では、創始300周年記念事業として校舎群のリニューアル工事を進めてきました。本プロジェクトのキーパーソンである、修道中学校 藏下一成教頭、中村達哉氏(設計ご担当、株式会社NTTファシリティーズ中国支店)、明賀朋昭氏(施工管理ご担当、株式会社フジタ広島支店)が、構想の背景や設計・施工のポイントについて語り合い、修道の新たな学び舎の魅力と価値に迫りました。
多くの命が失われた地に向く
原爆慰霊碑
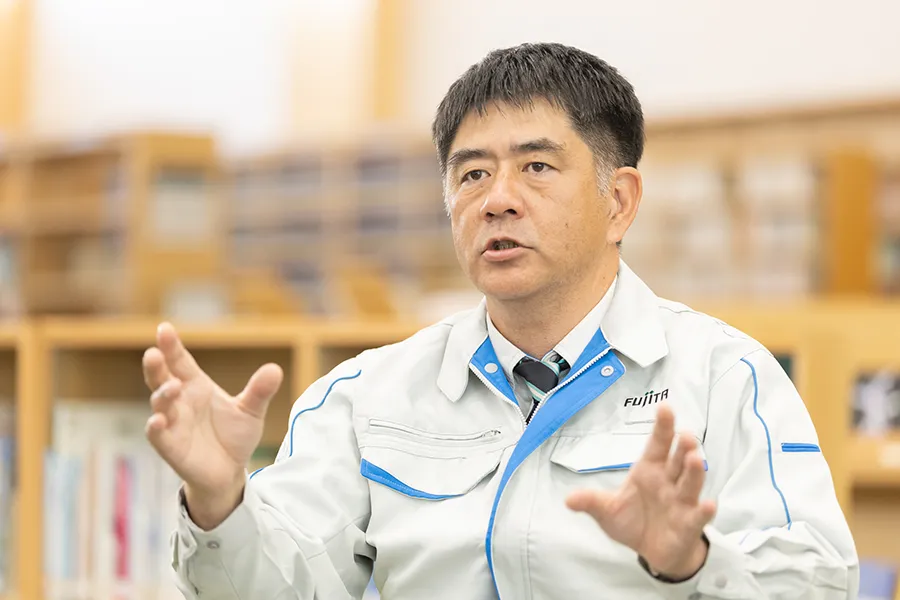
明賀朋昭氏(以下:明賀)
記念碑や石碑の移設作業は、特に緊張しましたね。破損させないよう細心の注意を払い、慎重に対応しました。重量が不明なものも多かったため、まず仮に持ち上げて重さを確認し、安全に移動させるための手順を現場ごとに綿密に計画して進めました。例えば、正門を入って右手に見える十竹先生の石碑(頌徳碑)は約7トンもの重量があり、数回仮置きを繰り返して移動しました。また、十竹先生の胸像も事前に視察した上で、移動方法を検討しました。同様に原爆慰霊碑についても、新たな配置に合わせて慎重に移設しました。

藏下一成教頭(以下:藏下)
原爆慰霊碑の移設に際しては、饒津神社さんに斎主をお願いして、御祭を執り行いました。旧制修道中学校では、旧雑魚場町(現在の国泰寺町付近)で建物疎開作業中だった2年生と教職員が多数、原爆の犠牲となりました。終戦の翌年に建立された慰霊碑は、今回が初めての移設だったのですが、慰霊碑に正対すると旧雑魚場町の方角に自然に体が向くように配置しました。なお、蔵(修道学問所之蔵)だけは動かせないので、結果的に蔵だけが少しポツンと取り残されたような印象になってしまったのは否めません。仕方のないことではありますが、空間全体の中でどう調和させるかという点では、今後も課題の一つとして残るのかもしれません。
中村達哉氏(以下:中村)
あの一帯は「歴史ゾーン」と位置づけ、慰霊碑や蔵、今回の工事で見つかった古い記念碑などを配置しました。
明賀
いくつかの記念碑が、過去の工事などによって埋もれてしまっていたようですね。
同窓生の絆、
母校への途切れぬ想い
藏下
そしてこの場をお借りして、本プロジェクトに対する同窓会のご協力にも感謝を申し上げたいと思います。同窓生からこれほど多額のご寄附をいただける中学校・高等学校というのは、全国的に見ても非常に稀だと思っています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今回のプロジェクトを通して、私たちの教育活動がいかに同窓生の皆様に支えられているかを、改めて実感しました。それは、卒業されてもなお強く学校に心を寄せてくださっている証であり、途切れることのない深い絆を感じさせるものです。
さらに、本校では恒常的なご寄附も受け付けているのですが、そちらにも毎年、相当な額をご支援いただいています。そうした継続的なご厚意にも、心から感謝申し上げます。

中村
この事業を進める中で、各種の届け出や協議のために市役所などの関係機関に出向くことがありました。その際、先方のご担当者が修道の卒業生ということが何度かありまして、驚くとともに、非常に印象的でした。
こちらが説明をする中で、「修道でこういうプロジェクトをやるんですね」、「こうなっていくといいですよね」といったように、むしろ先に背景を理解し、前向きなご意見やアドバイスをくださることもありました。協議の場で「これ、いい取り組みですね」と声をかけていただいたり、「自分が通っていた時はこうだったんですよ」と、昔の思い出を交えてお話しいただいたり…、地域に根づいた修道の存在の大きさを体感しましたね。
明賀
今回の工事を通じて同窓生の方々と直接お会いする機会は少なかったものの、修道を卒業された弊社の先輩方も多いので、「恥じない仕事をしよう」と常に考えていました。
特に印象に残っているのは、校地内のサッカー記念碑に刻まれた「藤田正明」という名前です。弊社の前身企業を築いた藤田一族の一人で、日本サッカー界でも知られる存在です。そんな縁もあり、このプロジェクトには特別な責任感を持って臨みました。さらに、上司や会社の上層部にも修道の卒業生が多くいることを知り、「その方々にも胸を張れる仕事を」との想いが原動力になっていました。
人と建物がつくる、
新しい修道のかたち
藏下
設備が整い、環境も大きく充実した今、これからは生徒自身が「この環境をどう使いたいか」、「どう学びを深めていくか」を主体的に考えることが大切になってきます。そうした意欲や発想が自然に広がり、周囲にも良い影響を与えていくことを期待しています。私たち教職員も、日々の教育活動をさらに充実させたいと考えています。「どう使えば学びが広がるか」、「こんな使い方もできるのでは」と試行錯誤を重ねています。
教職員と生徒が互いに発想を広げ合い、「こんな使い方もあるんだ」と新たな気づきが生まれる。そんな想像力豊かな学びの場になってくれればと願っています。
中村
今回の計画では、校内の各所に自然と人が集まれる“溜まり”のようなスペースをいくつか設けました。生徒の皆さんが談笑したり、気軽に集まったりする風景をイメージしています。
イベントデッキや校旗掲揚台にはベンチ状の構造も取り入れ、自由に過ごせる設計としました。さらに、そうした場所にはイベント利用も想定して電源コンセントを設置しています。今後、生徒さんや先生方の工夫によって多彩な使い方が生まれ、場の可能性が広がっていくことを楽しみにしています。


明賀
自分の人生の中で、「一番楽しかった時期はいつだったか」と振り返ると、やっぱり中高時代だったと思うんです。だからこそ、修道の生徒さんにも学校生活を活発に楽しく過ごしてほしい。「ここは手を挟みやすいかもしれない」、「この段差は転倒のリスクがあるかもしれない」といった細かな部分にも目を配りながら、少しでも安心して使ってもらえるように工夫を重ねてきたつもりです。新しくなった校舎を、のびのびと活用してもらえたら嬉しいですね。そしてそうやって使い込まれながら、この建物が長く愛されることを願います。
中村
300周年記念事業で新たな校舎や施設が完成しましたが、あくまで出発点だと感じています。これからさらに歴史を重ねていく中で、建物も少しずつ手を加えながら、大切に維持していきたいですね。
私たちはNTTの関連施設にも携わっており、局舎なども定期的に補修や改修を加えて長く使い続けています。そうした経験を活かして、この校舎も、丁寧に手を入れながら長く愛され続ける建物となるよう、今後もお手伝いしていけたらと思っています。

調和のある佇まいを見せる南館(左)と北館(右)
藏下
本当に心強いなと感じています。今回の工事を振り返ってみても、既存の建物と新しく完成した施設との間に、しっかりとしたトータル感、一体感のようなものが感じられるんです。まるで「最初からこういう計画だったのでは?」と思ってしまうほど、全体としての統一感が自然に保たれていて、その点には非常に感心しています。
だからこそ、今後また新たに何かをつくることになったとしても、これまで築いてきたこの調和を大切にしていきたい。例えるなら、生まれてきた子どもが、どこか両親に似ているような、そんな自然なつながりを感じられる校舎であり続けてほしいと思っています。
統一感と言えば、明賀さん、既存校舎との質感や色のバランスも見事ですね。同時期の建設だと言ってもわからないくらいですよ。

調和のある佇まいを見せる南館(左)と北館(右)
明賀
ありがとうございます。今回、北館を増築したのですが、すぐ隣に既存の南館があることが、施工上の大きな手がかりになりました。やはり隣接する建物との調和が大切ですので、職人さんにも「南館の雰囲気と合うように仕上げてほしい」と、常に伝えていました。機械ではできない部分ですね。
学びを成長を支え、
想像力を育む「器」に

藏下
まとめのような形になりますが、この新しい校舎は、生徒や教職員にとって、この先修道を離れても、ふと目を閉じた時に自然と思い浮かぶような、記憶に深く刻まれる存在になったように感じます。
また先ほども少し触れましたが、この校舎が生徒の“想像力”を育む場になってくれることを願っています。「ここでこんなことをやってみたい」、「あの場所を使ってこんなイベントを企画したい」といった発想が、友達との会話や生徒会の活動につながり、やがて先生たちを巻き込んだ大きな行事へと発展していく。そんなふうに、生徒たちの想いやアイデアが次々と形になっていくような、パワーを引き出す場になってくれたら嬉しいですね。
中村
このプロジェクトには設計段階から関わらせていただき、工事だけでも約3年、設計期間を含めると6年、プロポーザルから振り返ればさらに長い時間をかけて取り組んできました。その中で一貫して意識してきたのは、修道のシンボルである渡り廊下を、どのように次の時代へつなげていくかという点です。新しい渡り廊下も“修道の顔”として、多くの人の記憶に残る存在にしたいと願って設計を進めてきました。正直に申し上げると、以前の渡り廊下が印象的だっただけに、「それを超えられるか」という不安もありました。しかし今、完成した姿を見て、心から「これでよかった」と思えています。
渡り廊下をはじめとする新校舎が、生徒の皆さんはもちろん、地域の方や卒業生にとっても、新たな原風景となることを願っています。
明賀
2022(令和4)年5月2日の起工式からからほぼ3年が経ちます。中学校に入学して高校に進学するくらいの時間を、このプロジェクトに関わらせていただいたことになります。工事の進捗に応じて何度か人員が入れ替わり、最初から関わっている者は私だけになりました。旧食堂を技術室に転用する工事など、一部の工程はまだ残っていますが、先日ドローンで撮影した竣工写真に写る美しい校地を見て、大きな達成感を得ました。
「地域に開かれた学校」として、今後はこの外構空間がどのように活用されていくのか、とても楽しみにしています。今年の文化祭では、きっとこの新しい空間が賑わいの場として活躍してくれるのではないかと期待しています。
藏下
このプロジェクトには本当に多くの人の想いと仕事が重なっていたのだと、しみじみと実感します。設計・施工をはじめとする関係者の皆様には、長い年月をかけて丁寧に向き合っていただきましたし、在校生・教職員・保護者・そして同窓生の皆様からも、さまざまな形で支えていただきました。
この新しい校舎が、生徒たちの学びと成長を支える器となり、彼らの記憶に残る原風景として、未来に引き継がれていくことを願っています。この場所が、これからも多くの創造と挑戦、そして笑顔の生まれる場であり続けることを信じて、この場を締めくくります。本日は、貴重なお話をありがとうございました。