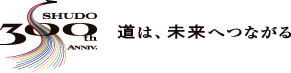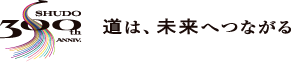MESSAGES
修道中学校 藏下一成教頭(中央)、株式会社NTTファシリティーズ中国支店 中村達哉氏(左)、株式会社フジタ広島支店 明賀朋昭氏(右)
VOL.3
〈座談会〉 修道300年の新たな「器」―
新校舎が導く“修道進化論”
─前編─
修道中学校・修道高等学校では、創始300周年記念事業として校舎群のリニューアル工事を進めてきました。本プロジェクトのキーパーソンである、修道中学校 藏下一成教頭、中村達哉氏(設計ご担当、株式会社NTTファシリティーズ中国支店)、明賀朋昭氏(施工管理ご担当、株式会社フジタ広島支店)が、構想の背景や設計・施工のポイントについて語り合い、修道の新たな学び舎の魅力と価値に迫りました。
地域に開かれた校舎と
空間づくりを目指したい

藏下一成教頭(以下:藏下)
本校では300周年事業として、旧本館をはじめとする校舎群のリニューアル工事を選びました。まずはその理由から話を始めましょう。
旧本館は1978(昭和53)年に建てられたもので、耐震化などの改修をしながら使用してきましたが、設備面でも時代の変化に対応しきれなくなっていました。建て替えを検討し始めたタイミングと300周年という大きな節目が重なり、また周年を機に、地域に開かれた新しい校舎を目指したいという想いもあり、リニューアルに踏み切りました。

中村達哉氏(以下:中村)
設計にあたって特に意識したのは、藏下先生のお話にもあった「地域に開かれた空間」です。例えば、従来は校内で完結していた中庭を外部にも開く設計や、修道広場の新設などを通じて、地域の方々にも学校の雰囲気や活動が伝わる、魅力ある空間を目指しました。

明賀朋昭氏(以下:明賀)
最近ようやく外周の仮囲いを外したのですが、近隣の方々が見学に訪れたり、写真を撮っていかれたりする姿が多く見られますね。また、班活動の対外試合で来校された保護者の方々も、外構周辺を興味深そうにご覧になっています。そうした光景からも、新しい校舎が地域に開かれているという雰囲気が自然と伝わっているのかな、と感じています。
藏下
図書館をはじめ、今回刷新したさまざまな施設に対して、生徒や教職員、保護者の方々から「使いやすくなった」、「このままきれいに使い続けたい」といった声を多くいただいています。
併せてセキュリティ面への評価も寄せられています。一部区域ではカード認証による出入管理を導入し、利用履歴の記録も可能です。見た目には開かれた空間でありながら、しっかりとした安全対策が施されていることが、安心感につながっていると感じますね。
渡り廊下を起点に、
コンセプトが具体化
藏下
設計の依頼先を選定するにあたり、複数の設計会社から3Dパースなどを用いた提案をいただいたのですが、NTTファシリティーズさんの案が最も私たちの感覚にフィットしたんですね。言葉では説明しづらいのですが、感覚的に「しっくりきた」提案でした。敬道館を図書館に転用する発想など、「既存の建物を活用してコストを抑える」という姿勢が見られたことも印象的でした。まあ、最終的にはそれなりの費用がかかりましたけれども(笑)。
設計側の感性や考え方に、私たちの想いと重なる部分が多かったことが、お願いする決め手になったと感じています。打ち合わせを重ねる中で自然と信頼関係や共通理解が生まれ、それがプロジェクトの出発点として大きな意味を持っていたと思います。
中村
「地域に開かれた、開放感のある校舎」というコンセプトは、渡り廊下をどう設計するかという議論を経て、より明確になりました。
明賀
修道のシンボル的な存在だった渡り廊下を架け替えるのは、大きな転換でしたね。

新しく架け替えられた渡り廊下
中村
はい、おっしゃる通りです。実は、基本設計の段階では屋内型の閉じた構造を想定していましたが、最終的に、修道広場のイベントデッキと接続した開放的なデザインに至りました。また、旧渡り廊下に代わる新たな象徴的要素としての役割も意識しましたね。こうした再検討の過程で外構計画全体も見直し、「地域に開かれた校舎」というコンセプトが具体的な形になっていきました。

新しく架け替えられた渡り廊下

開放感のある外構と、旧制中学校時代から受け継がれている門柱
藏下
それに加えて、外構、特に校地外周の柵などについても、「できるだけ低くして、外から中の様子が見えるようにしよう」という考えがありました。
例えば、「ちょっと入ってみたいな」と思わせる雰囲気はあるけれど、実際には勝手に入れない、そんな距離感が「開かれた学校」のイメージにつながるのではないかと。完全にオープンにするわけではないけれど、視覚的にも心理的にも閉ざさない。そういう在り方を目指しました。

開放感のある外構と、旧制中学校時代から受け継がれている門柱
互いの信頼から生まれた、
学校×設計×施工の連携力

藏下
長期にわたるプロジェクトだったこともあり、中村さん、明賀さんとは何度も打ち合わせを重ねました。素材や色の選定など細部まで確認し、「これでいきましょう」と、なぜか私が決裁者のような立場になり、即断即決で進める場面も多かったですね(笑)。
図面もたくさん拝見し、「ここはどうする?」といった具体的な相談も頻繁に行いました。完成はしっかりイメージしていたつもりでしたが、実際の建物には図面にはない空気感があり、「図面より良いものができた!」と実感できて、本当に嬉しく、感慨深いです。
中村
設計がまとまって、インテリア、エクステリアの素材やカラーを決めていくわけですが、私が多数のサンプル・カタログから「これでよろしいでしょうか?」と伺うと、藏下先生は即断即決で「それでいきましょう」と応じてくださり、そのスピードに本当に助けられました。
先生は美術を専攻されていて、選ぶもの一つひとつにこだわりがあり、「そう、それですよね!」と私自身も共感する場面が多々ありました。先生に確認いただけば、間違いないという安心感もありました。完成した空間には先生のセレクトが随所に活かされた「本当に素敵だな」と感じられる仕上がりになったと思います。
明賀
施工においては、お二人のイメージを大切にしつつ、機能面にも十分配慮しました。生徒の皆さんが日常的に使う校舎だからこそ、安全性や使いやすさは重要で、什器設置時の床の強度など、構造面も丁寧に確認しながら進めました。
また、学校生活と並行しての施工ですので、生徒さんの安全や生活動線についても先生方と綿密に連携しながら対応しました。さらに電気系統の盛り替えなど、地中の見えない部分を含めてインフラ面でも大規模な更新を実施したのですが、設備を止めずに工事を進める必要がありますので、難しさも伴いましたね。登下校時は工事車両の進入を一切禁止とするなど、安全管理のルールを徹底し、無事故で工事を終えることができました。
“暮らす人”の想いを、
対話から汲み取る

藏下
「新しい校舎でどんな学校生活を送りたいか」、「どんなふうに活動したいか」といった一人ひとりの想いを丁寧に汲み取ることも大切にしました。すべての要望をそのまま形にすることはできませんが、まずは声に耳を傾け、その気持ちを受け止めたうえで、それらを支えるインフラや環境を整えるというプロセスを重視しましたね。
そうした積み重ねによって、生徒や教職員の想いが少しずつ形になり、「修道らしさ」と呼べる雰囲気が自然と生まれてきたように感じています。私たちとしても、その想いの実現に寄り添って仕事をしていた、という実感があります。

中村
関係者の皆様の意見はかなり広くお伺いしましたね。
藏下
そうですね、学内では何度も委員会を開き、そのたびに設計の中村さんにもご同席いただきました。毎回、突拍子もないアイデアから実現可能なものまで、さまざまな意見が飛び交い、会議が終わる頃には私も中村さんもヘトヘトでした。
そうした中でも、「これは法的に難しいです」、「予算的に厳しいかもしれません」といった現実的な判断や丁寧な「ごめんなさい」を交えつつ、“修道で暮らす”人たちの想いを汲み取ろうとする姿勢が、常にプランに込められていたように感じます。その真摯な姿勢に私たちも安心して任せることができましたし、このプロジェクトをご一緒できて本当に良かったと心から思っています。
中村
よく覚えているのは、十竹ホールで教職員の皆様の前に立ち、私が数分間お時間をいただいて、設計の内容について説明をした時のことです。始めは一人でずっと話し続けるような形でしたが、説明が終わると、さまざまなご意見やご質問をいただきました。ご意見にしっかり耳を傾けながら一つひとつ対応しつつ、必要に応じて藏下先生にもご相談をしながら進めていきました。
藏下
そうそう、ありましたね。十竹ホールで職員会議をやって、中村さんに設計内容のプレゼンをお願いしたんです。するとその後、中村さんの周りに人だかりができて、「これはどうなっているの?」、「あれはこうすべきじゃないか」と、質問攻めに。それなのに、誰も助けに入らず、私も傍らで見守るばかりで(笑)。「中村さん、かなり困ってるなぁ」と思いながら見ていたのを覚えています。それでも中村さんは、その場で一つひとつ丁寧に対応し、きちんとメモを取って、後日しっかり報告してくださいましたね。
中村
実現はしなかったのですが、屋上緑化をして理科の授業に活用できないか、というご意見もいただきましたね。
藏下
外壁も緑化したいという意見もありましたね。実現性はともかく、関わりたいという気持ちの強い人が多いと思うんですよ。有難いですね。それをまとめ上げるのは、お互い大変でしたけどね(笑)。
中村
今回のプロジェクトを通して強く感じたのは、先生方や関係者の皆様が修道に対して非常に深い思い入れを持っておられるということです。それぞれに「修道はこうあるべきだ」という考えや、学校への愛着があり、その熱意を随所で感じました。だからこそ、建物が完成した時に「やっぱり前の方がよかった」と言われたらどうしよう…という不安もありました。今のところは概ね良い反応をいただいていますが、そうした声が出る可能性は常に意識していました。
デザイン・設計・施工の
こだわりと挑戦

修道のシンボルとして長く愛された旧渡り廊下
中村
近年の学校建築の傾向としては、少子高齢化や学校数の減少といった社会的背景の中で、それぞれの学校が独自性や個性を強く打ち出す方向にシフトしていると感じています。環境面への配慮も重要視される中で、「その学校らしさ」を建築でどう表現するかを求められる時代です。
その意味で、修道ならではの個性として強く意識したのが「渡り廊下」の存在です。これは他の学校にはない象徴的な要素であり、新校舎でもその印象を大切にした設計を心がけました。旧渡り廊下にあったアーチ状の窓、あの柔らかな形状を継承しながら、新校舎では円弧や半円のモチーフを随所に取り入れています。例えば、イベントデッキの円盤のような意匠や広場の構成など、円がつながるような空間構成を意図しました。

修道のシンボルとして長く愛された旧渡り廊下

修道マークが施された修道広場
環境面でも、自然光を取り入れつつ、必要な部分では制御する工夫をしています。具体的には、スリット状の窓を部分的に設けて採光しつつ、西日が直接入りすぎないような配置やデザインに配慮しました。
そして、もう一つお伝えしたいのが「修道マーク」の活用です。校内のさまざまな場所にさりげなく配置していて、いくつか例を申し上げると、修道広場の床面やガラス面の衝突防止シールにマークを施しています。ディズニーランドの「隠れミッキー」のように、見つける楽しさを感じていただけるよう工夫しています。

修道マークが施された修道広場
藏下
修道マークが校内にいくつあるか、クイズができそうですね。修道マークの活用についても、もちろん即決しましたよ(笑)。

中村
設計者として、少し挑戦的なデザインにも取り組みました。その一例が、渡り廊下の先に設けた楕円形のステージ空間です。柱をあえて斜めに配置し、屋根にも傾斜を持たせるというインパクトのある意匠ですが、構造的・施工的には非常に難度の高い設計です。柱は垂直、梁は水平というのが一般的な構造ですが、このステージでは柱が斜めに立ち、その上に勾配のある楕円形の屋根が載るという複雑な構成です。しかもこれは学校側からの要望ではなく、私たち設計側からの提案でした。

正円のように「中心」を強調する場は、日本的な感覚ではかえって人が中心を避け、周囲に集まる傾向があります。そこで今回は、中心の力を和らげ、人が自然と集まりやすくなるよう、あえて楕円形を採用しました。芝生広場の修道マークも楕円形をベースにしており、上から見るとわずかに横に広がったフォルムになっています。こうした形状の工夫によって、空間に柔らかさと広がりをもたせ、自由な使われ方が促されるように設計しました。
明賀
施工の立場から言えば、最もシンプルで施工しやすいのは四角い建物です。しかし、今回のように「円」や「楕円」といった形状が加わると、施工の難度は一気に上がります。
中村さんもお話しされた通り、今回のイベントデッキは柱が斜めに配置され、屋根にも傾斜がある非常に複雑な設計でした。鉄骨の建て方について社内の施工検討会で議論した際も、「どうやって建てればいいのか」と戸惑いの声が上がったほどです。
そこで参考にしたのが、同様の構造を持つ施設でした。「ひろしまゲートパーク」や「エディオンピースウイング広島」などを実際に見学し、施工方法を調査しました。また過去に類似のプロジェクトに携わったメンバーからも知見を集めて、解決の糸口を見出していきました。期限いっぱいまでかけて、鉄骨が建ち上がった時は嬉しかったですね。下部の躯体も楕円形で難度が高く、当社の技術部も加わって構造の成立性や施工方法を慎重に検討し、最終的にこの複雑な構造を実現することができました。
中村
明賀さんとは何度も打ち合わせをさせていただきましたね。施工チームには本当に大変なご苦労をお掛けしました。
明賀
何と難しく、施工者泣かせの設計なんだろうと思いましたね(笑)。
その他の施工面の特色についてご紹介しますと、まず渡り廊下は、鋼線を入れて橋梁のようなイメージで造っています。また北館の壁面に使われているアルミ製のクロスバーは新製品で、全国で初めての施工事例となりました。中学・高等学校では修道が全国初となる、スカッシュコートの設置も大きな特色ですね。実は広島にはスカッシュコートがほとんどなく、私たちにとっても未知の領域だったんです。専門業者と何度も打ち合わせを重ね、細部まで丁寧に検討しながら、一つひとつ形にしていきました。

北館壁面のクロスバー越しに修道広場を望む

中高で全国初の設置となったスカッシュコート