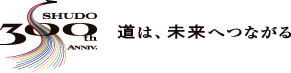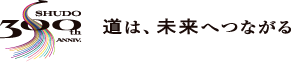MESSAGES
写真左から株式会社日建設計 田中公康氏、広島修道大学財務課 酒井健志郎課長補佐、株式会社フジタ広島支店 吉田哲朗氏
VOL.4
〈座談会〉 未来を拓く、未来へつなぐ
―新体育館が描く
SHUDAIのビジョン
─後編─
広島修道大学では、学園創始300周年記念事業として新体育館の建設を進めています。従来の体育施設の枠を超え、多彩な機能を備えた場として再構築される新体育館。プロジェクト発足から一貫して携わる広島修道大学財務課 酒井健志郎課長補佐、田中公康氏(株式会社日建設計)、吉田哲朗氏(株式会社フジタ広島支店)が、それぞれの立場から見たプロセスの背景、そしてこの体育館を通して描かれる大学の未来像などについて語り合いました。
大学・地域にとって開かれた
空間を提供する体育館

酒井健志郎課長補佐(以下:酒井)
本体育館の基本計画では、3つのコンセプトが掲げられています。前編でも触れましたが、学生・教員・職員によるワークショップから導かれたコンセプトです。
その一つ目は「大学・地域にとって開かれた空間を提供する体育館」です。学生、教職員はもちろんのこと、「広島修道大学」らしい、地域にも開かれた体育館とします。今後地域の方々にも体育館を利用できるような規程を整備する予定としています。地域のスポーツ大会などがある場合は、ぜひ一度ご相談いただければと思っています。

田中公康氏(以下:田中)
新体育館はキャンパス内の建物の中でも、正門から最も近い場所に位置しています。外観にはガラス張りのファサードを採用し、訪れる人を迎える「顔」として、開かれた印象を演出しました。さらに、エントランスに面したトレーニングルームもガラス張りとしたことで、空間の広がりを感じていただける設計となっています。

吉田哲朗氏(以下:吉田)
多くの方が利用する体育館ですので、安全面への配慮も重要です。例えば、大空間を構成する鉄骨には耐火塗装を施して、耐火皮膜を確保しています。万が一の火災でも、鉄骨が熱を受けると塗装が発泡して断熱層を形成し、鉄骨の倒壊を防ぐという仕組みです。耐火塗装の施工ボリュームは約9,000平方メートル以上で、仕上面(内装の最も表面の部分)の中でも大きなウエイトを占めています。これほどの規模で耐火塗装を施工した事例は、他にはあまりないと思います。また、工事を進めるにあたり、隣接する既存体育館への臭気対策には細心の注意を払いました。

耐火塗装が施された鉄骨
田中
先程は、コスト面からスケルトン構造を採用した理由をご紹介しましたが、この構造にはもう一つ大きな利点があります。それは、天井の落下リスクがなく、災害時にも安心して利用できるという点です。本体育館は、広島市の指定緊急避難場所にも指定される予定と聞いています。安全性の観点から見ても、意義のある選択と言えるでしょう。
オープンで多様な
「居場所」を創造する体育館

酒井
2つ目は「オープンで多様な居場所を創造する体育館」です。多様な学生たちの居場所となる空間を作り、単なる体育施設としての機能だけでなく、多様な利用目的をもった利用者が集い、つながることができるオープンな場を創造する体育館とします。
田中
体育館の大きな庇の下やロビー空間は、授業の合間やお昼休み、下校時のバス待ちの時間などに、憩いの場として活用いただけると嬉しいですね。
また、体育館の前に新たに設ける広場「SD connect」は、学生同士、学生と教職員、あるいは学外からの来訪者など、さまざまな人々が憩い、交流することを意図した場所です。7号館側には、屋根付きの広場「SD terrace」も新設しました。人工芝の上を心地よい風が通り抜け、過ごしやすい日陰の居場所を作っています。ここでお弁当を食べたり、友達と自習したり、時にはリモート授業を受けたり――思い思いに活動できる、皆さんの「居場所」になればと考えています。
酒井
体育館の2階には同窓会室も設けました。同窓会室はもともと講堂にあったのですが、建物自体の老朽化や、防音設備などの面で業務に支障を来すこともあったため、新体育館へ移設することになりました。同窓生の皆様の新たな拠点となればと思っています。
2025年のスタンダードを
体現する体育館
酒井
3つ目は「2025年のスタンダードを体現する体育館」です。バリアフリーなどのユニバーサルデザインを実現するSDGs、低炭素社会に対応するカーボンニュートラルを取り入れ、デザイン的にも機能的にも、快適で利用しやすくしながらも、時代に流されず、長く愛され続ける体育館とします。

壁面ルーバー
田中
メインアリーナやサブアリーナには、地域の自然素材を用いて、温かみを感じられる空間を目指しました。壁面のルーバーやベンチの芯材には中国地方産の杉の間伐材を使用しています。間伐材を使用することで環境にも配慮した建材となっています。
また、地上の骨組みはすべて鉄骨造とし、建物を軽量化しました。建物を軽く造るということは、余計な部材を使わないということ。コスト圧縮だけでなく、地球環境にやさしい建物を目指しました。
酒井
既存体育館が竣工した50年前と現在とでは、環境や価値観が大きく変化しています。50年前に館内の冷暖房を整備しているスポーツ施設は、ほとんどなかったのではないでしょうか。しかし近年では、夏季の熱中症対策は必須です。
吉田
カーボンニュートラルに寄与するという観点では、新体育館の屋根には太陽光パネルを設置し、体育館の年間電気使用量の約5.7%を賄える発電設備を備えています。また災害時には、その太陽光から発電した電気を利用できるコンセントも整備しています。
田中
広場に敷設する人工芝は、トウモロコシ、サトウキビなどの植物由来のバイオポリエチレンを一部に使用した環境配慮型の人工芝を採用しています。現代建築では、環境への配慮も欠かせませんね。
酒井
既存体育館の課題の一つだった観客席の急勾配も、新体育館では解消されています。固定座席数は少し減りましたが……。
田中
そうですね。新体育館の固定座席数は822席で、既存体育館よりも3~40席ほど減少していますが、観客席と同じ3階レベルに位置する卓球場には、スタッキングチェアを並べることが可能です。これにより、アリーナ面で1500席、固定座席で822席、さらに卓球場を加えると、既存体育館と同じくらいの人数を収容することが可能です。
また、新体育館にはスカッシュコートも設置しましたが、専用コートを持つ大学は珍しいですね。

メインアリーナ観客席

施工中のスカッシュコート
酒井
はい、中四国地域の大学では初だと聞いています。本学のスカッシュ部は、全国大会にも出場実績のある強豪なのですが、これまでは学外の施設を利用して練習を行ってきました。新体育館に自前のコートが完成したことで、より充実したトレーニング環境が整い、今後さらなる活躍を期待しています。
広島修道大学の未来を描く
新たなシンボルとして
田中
この体育館の魅力は、内部に間仕切り壁がほとんどなく、空間全体を一望できる開放感にあります。さまざまな活動が同時に展開されている様子が一目で見渡せることで、それぞれの活気が互いに響き合い、スポーツのエネルギーを一層高める。そんな相乗効果を生む空間を目指しました。
スポーツに取り組む学生たちの活気が建物全体に満ちあふれ、そのエネルギーが外部にも伝わっていくような、訪れた方々に強い印象を与える施設となることを願っています。
そして「SD connect」「SD terrace」とともに、大学に集う人々の「居場所」として、長く親しまれてほしいですね。
吉田
どの建物も完成直後はがらんとしていて、無機質で殺風景なものです。設備や備品が搬入され、実際の運用が始まって初めて、その建物は本来の役割を果たし始めます。利用される皆さんにとって快適で、「良い建物だ」と感じていただけること、そして運用が始まった後に、建物がキャンパスの風景に自然と溶け込んでいる姿を見ることが、施工者として何よりの喜びです。
酒井
新体育館は、単なる体育施設ではありません。同時に整備している「SD connect」「SD terrace」とともに、学生の皆さんが自由に過ごせる「居場所」として活用されることを願っています。今後「SD connect」や「SD terrace」で昼食を楽しめるように、キッチンカーを呼ぶ計画も検討しています。
体育館は2025(令和7)年9月8日に竣工式、その後引っ越し期間を経て、12日の供用開始を予定しており、竣工式ではスペシャルゲストをお招きして、こけら落としのイベントを計画中です。
新体育館の3つのコンセプトは、広島修道大学が目指す未来像にもつながるものです。この体育館が本学の未来を描く新たなシンボルとして、学内外の皆様に広く親しまれることを願っています。
本日はありがとうございました。